農民美術におけるアマチュアの性質
石川義宗
日本デザイン学会|長野大学
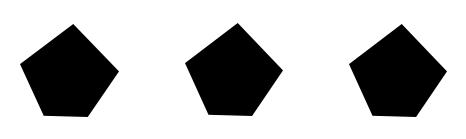
山本鼎(1882-1946)は1919年に農民美術の運動を長野県小県郡神川村(現・上田市国分)ではじめた。その運動において農民たちは木工から染織まで様々な工芸品を作った。その表現は村の日常をモチーフとしており、例えば、木皿の表にはホオズキが赤漆によって表現されたものあれば、鴨が彫られたものもある。また、蚕や蝶が水彩画風に描かれたものもある。木彫の人形は高さが5センチから3センチ程度で、農夫や郵便局員、スキーやスケートを楽しんでいるものもある。染織の多くは植物をモチーフとしている。花、茎、葉を左右対称に配置したテーブルクロスは、水色や桃色などの鮮やかな糸で刺繍してある。
神川村は製糸業で栄えた上田市の郊外にあり、広大な養蚕コミュニティーの一角を担っていた。上田市は蚕都と呼ばれるほど繁栄し、洋風建築が幾つも建てられ、路面電車が市民の足となり、映画館や演劇場が市民に娯楽を提供していた。市街地から神川村まで直線距離は10キロほどであり、鉄道が敷かれていた。神川村にもカフェができ、街灯が道を照らし、大正デモクラシーの機運に乗じて信濃自由大学といった市民講座も催されていた。
上記のような農民美術の表現について、民芸運動をはじめた柳宗悦(1889-1961)は批判的であった。彼は『民藝と農民美術』(1935)において農民美術が地域の土着のものではなく、西洋化された表現であることを批判したのである。しかし、神川村は都市文化に近接し、大正デモクラシーが波及した土地であり、その生活文化は和と洋が入り混じっていた。農民美術は当時の世相を素直に捉えたものであり、その通俗性は農民たちの真摯な眼差しを証しするものだと言える。
山本は手仕事を重視していたが、農民美術の制作の実態は神川村の産業に即したものであった。すなわち、それは養蚕業における工場制機械工業の普及と軌を一にしている。『神川村略史』(1973)によると、農民美術の制作に角ノミや自動カンナといった木工機械が導入されていたことがうかがえる。農民たちにとって手仕事とはすでに機械加工と分かちがたいものであり、両者は対立するものではない。むしろ、精緻な意匠図が残されていることから、農民美術は計画的に設計されたものであり、手仕事と機械加工の合理的な中庸を基本にしていたものであったと言える。
農民美術は農閑期を利用した産業だと言える。しかし、村の文化活動という一面もある。山本や農民たちは文化祭を催し、ストリンドベリの劇を演じたり、バッハやヘンデルのレコードを鑑賞したりした。広義にはこれも農民美術の運動の一部である。また、山本が同時期にはじめた児童自由画運動や青年たちによる信濃自由大学と連携し、農民美術は村の地域文化をかたちづくっていたのである。この全体から見ると、農民美術はあくまで美術の可能性を前提とした運動である。言い換えれば、農民美術は村の日常の中に留まり、労働において醸成され、農民たちを癒した芸術の姿であった。
1935年に農民美術は財政的にいったん行き詰まってしまう。山本は私財を投げ打ってまで対策に翻弄するが、工房は閉鎖してしまった。この点では、当時の農民美術は産業として未熟だったと言えるかも知れない。しかし、農民美術はアマチュアの領分に芽吹いたものだったからこそ自由闊達な作品群が生まれたことも事実である。