重度・重複障害児からアートとスポーツの根源を考える
遊戯論を視座として
池田吏志
美術科教育学会|広島大学
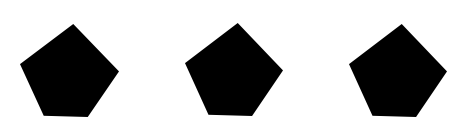
今回のシンポジウムは、「芸術とスポーツ」がテーマでした。私の発表では、一般的に異なるものとして枠づけられている両者を、重度・重複障害児といわれる身体的、知的に重い障害のある子どもたちの造形活動を通して再検討することで、両者の胚胎を探ってみることでした。この目的を設定した理由は2点あります。1点目は、発達の初期段階に見られる遊びの様相を、遊戯論を視座として現象学的に捉えることで、芸術とスポーツが分化する以前の根源を探ってみたいと考えたため、2点目は、特に2010年以降、C. PenkethやM. Kallio-Tavinらを中心に海外の美術教育研究で試みられている、障害のある人達のエンボディメントを通した常識や前提の問いなおしをしてみたいと考えたためです。エンボディメントとは、身体と自己と文化を混然一体として捉える視点や、特定の種類のレンズを通して世界を認識することとされます(R. Adams et al.)。今回の発表では、重度・重複障害児の身体という、一見芸術とスポーツからは最も縁遠いように思われている地点から両者を捉え直すことで、社会的・文化的・政治的に形成された芸術やスポーツの規範や自明性に対して、ささやかですが拡大的な議論の余地を示したいと考えました。
今回主役となった重度・重複障害児とは、本人及び支援者の双方が言語もしくは非言語的手段による意思疎通が困難で、なおかつ身体、視覚、聴覚等、他の支援を併せて必要とする子どもたちです。今回の発表では、ある一人の子ども(Aさん)を取り上げ、特別支援学校の小学部で実施されたアクション・リサーチでの造形活動の様子や、全8回の授業で見られたAさんの行動変容を紹介しました。具体的には、授業開始時に支援方法が全く適合せず、Aさんの活動意欲を高められなかったこと、しかし、その後の継続的な教具の改善により、Aさんが活動に興味を持ち始め、第7回や8回の授業では教具で遊ぶことを楽しんだり、材料の変化に注意を向けたりしたことを、写真やビデオで紹介しました。その後、Aさんと教具と教員による支援との関係を整理したモデルを用い、Aさんの行動変容の段階を、①「無関心」②「定位(教具に注意を向けること)」③「リーチング(教具に手を伸ばすこと)」④「把持」⑤「遊び」⑥「遊びで生じる変化への定位」⑦「変化の結果(作品)への定位」の7段階で示しました。特に造形活動では、子どもが一定時間教具を持ち続ける④の「把持」や、教具を使って遊ぶ⑤の「遊び」が現れることが、意欲的な活動を実現できるか否かの分水嶺になっていることを示しました。
では、重度・重複障害児の造形活動で鍵となる「把持」や「遊び」とはどのような状態なのでしょうか。哲学者の坂部恵は、五感の中で視覚、聴覚、嗅覚、味覚を表す場合は助詞に「○○を」、が用いられるのに対し、触覚の場合だけは、「机にふれる」といったように「○○に」が用いられていることを指摘しています。その理由として、「ふれる」は、主体と客体の関係がいずれか一方向に働くのではなく転換の可能性を有し、ふれるものとふれられるものの相互嵌入、転位、交叉といった力動的な構造を持つためだと述べています。そしてこの関係は「風景に遊ぶ」と言われる場合と似た構造を持つとも述べています。同様に西村清和も、手のひらの中で鍵束をさわったり動かしたりする状態を例に挙げ、連続的にものが動き、さわり・さわられる状態で起こる相互嵌入的な状態を「玩ぶ」状態、つまり「もちて・遊ぶ」状態としています。西村は、この状態を「ものとわたしとのあいだで、いずれが主体とも客体ともわかちがたく、つかずはなれずゆきつもどりつする遊動のパトス的関係」として、これを「遊戯関係」と呼んでいます。このように、坂部も西村も、主客分かちがたく、相互嵌入的で力動的な関係そのものを「遊戯」として捉えていることが分かります。
次に、遊戯と芸術、また、遊戯とスポーツとの関係に言及している学者の見解をみてみます。例えば、ハンス=ゲオルク・ガダマーは、遊戯(Spiel)と芸術経験の共通点として、それらはいずれも能動的であると同時に受動的な「中動相的性質を有している」と述べています。この点は、先ほどの坂部、西村と共通しますが、ガダマーの主張の重要な点は、その経験が、遊んだりつくったりしている人の主体性を喪失させ、遊戯や芸術そのものが主体として移り変わることを指摘している点です。このことは、ヨハン・ホイジンガも同様の見解を示しており、主著の『ホモ・ルーデンス』では、文化は遊びとして、もしくは遊びから始まったのではなく、遊びの中で始まったのだと述べています。彼が文化として挙げているものの中には、芸術やスポーツも含まれます。
これらのことを踏まえ、重度・重複障害児を含めた芸術とスポーツの根源的な共通点を仮に定義してみますと、次のように言えるのではないでしょうか。重度・重複障害児を含む芸術とスポーツの根源的な共通点とは、中動相(能動的であり受動的である状態)で生起される主客未分化の状態に没入している行為であり、さらに、ある経験が経験する者を変化する連続体の只中に引き入れ、主体を喪失させ、経験そのものの支配下に置く状態である、と。つまり、芸術やスポーツの根源として、行為者が主体となるよりも、行っていることそのものが主体に置き換わり、行為者を没我させ、その経験の只中に引き込む動的な状態といえるのではないかということです。この状態は、フロー(ミハイ・チクセントミハイ)と呼ばれることもありますが、フローが行為者自身と課題とを分けて捉え、見通しや目標を設定して実現されるのとは異なり、ここで検討した状態は、無自覚に起こることがあるということです。もちろん、オリンピアンや熟達した芸術家が経験する没我の状態は、一般人である私達の想像の域をはるかに超えた所にあるのかもしれません。また、行為者の年齢やキャリア、そして熟達の度合いによっても現れる状態は異なるのかもしれません。しかし、いわゆる競技での勝敗や作品・演技の芸術性とは関係なく、今回検討した根源的な状態はすべての人に同様に起こり得ると考えます。
今回のシンポジウムでは、オリンピックイヤーに行われた芸術とスポーツをテーマにしたシンポジウムに、重度・重複障害児を主題とする発表を含めていただきました。このことは、「人」を広範に捉えるポストヒューマン(ロージ・ブライドッティ)の議論や、モノと人との関係を問いなおす新しい唯物論(K. Barad)等への接続可能性を持ちます。例えば、今回の事例に見られる主客の相互嵌入という状態が、教具と表現者との関係を越え、スポーツにおけるAIと審判員のジャッジの問題やアスリートと評価者の問題等に重なり、さらには、障害の有/無(dis/ability)とは何か、また、テクノロジーと人間が生み出す新しい場や空間とは何かといった議論にも広がることを期待しています。
最後になりましたが、このたび推薦くださった美術科教育学会の先生方、またコロナ禍の難しい時期に議論と共有の場を設けてくださった藝術学関連学会連合の先生方に改めてお礼申し上げます。